news
【イベントレポート】オンラインイベント ジャーナリズムXの針路 ~日本社会をもみほぐすジャーナリズムは可能か~(2022年4月17日開催)

バブル崩壊以来の停滞から抜け出せず、いまや“周回遅れ” どころか“難破” にさえ例えられる日本社会の硬直と閉塞はジャーナリズム自身も蝕んでいますが、その辺縁ではさまざまな萌芽も生まれつつあります。境界を超えるしなやかさ、したたかさとは何か――。ゲストに、 沖縄タイムス社編集委員の阿部岳さん、著述家の師岡カリーマ・ エルサムニーさんをお迎えし、 地方や海外の視点を交えて考えます。
◆ゲスト
・師岡カリーマ・エルサムニーさん(著述家)
・阿部岳さん(沖縄タイムス社編集委員)
◆主催
ジャーナリズム支援市民基金
◆後援
一般社団法人アクト・ビヨンド・トラスト、公益財団法人 庭野平和財団
▼当日の動画はこちら
《開会の挨拶》
星川:みなさん、こんにちは。今日のかなり刺激的なオンラインイベントにようこそ。このイベントは、市民側からジャーナリズムを応援しようと3年前に立ち上げたジャーナリズム支援市民基金の主催で、私はその代表幹事を務める星川淳です。
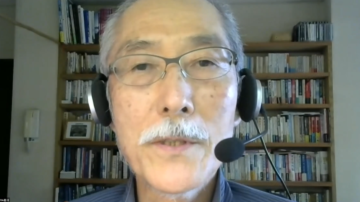
ジャーナリズム支援市民基金 代表幹事 星川淳
私自身、著書・訳書80冊を超える書き手ですけれども、これまでジャーナリズムとの境界線上にあるような仕事はしたことはあっても、厳密な意味ではジャーナリストではありません。このジャーナリズム支援市民基金は、私と同じようにジャーナリストではないけれども、いろいろな市民活動に長く取り組んできたメンバーが運営やアワードの選考などをしているのが特徴です。環境、人権、農業など、かなり幅広い社会課題に関わってきた人たちがメンバーです。僕は、国際環境NGOグリーンピース・ジャパンの事務局長を以前に務め、いまは一般社団法人アクト・ビヨンド・トラストという環境分野の市民活動を助成する基金を運営しています。
こうした市民活動に取り組むなかで、ジャーナリズムが健全に機能してくれないと、自分たちが取り組んでいる問題を広く社会に知ってもらったり、解決に向けて社会を動かしたりすることが難しいことを痛感しました。そこから、この基金を思い立ち創設しました。このあとに紹介する「ジャーナリズムXアワード」はその第一歩ですけれども、もう少し知名度をあげて財源をつくり、ジャーナリズムのいろいろなプロジェクトを支援できる体制にしていくことが、この基金のそもそもの目的です。
《ジャーナリズムXアワードについて》
司会(美濃部):続きまして、事務局よりジャーナリズム支援市民基金が運営している表彰形式の企画「ジャーナリズムXアワード」について簡単なご説明をさせていただきます。いま代表幹事の星川からもありましたように、自由で公正な社会を創るためにはジャーナリズムが本来の力を発揮できるようになってほしいという願いのもと、当基金は2019年にジャーナリズムXアワードを創設しました。今年で第3回目を迎えています。
応募の対象は、自薦他薦、アマやプロ、年齢や国籍も問いません。個人やNPO、民間企業など、何かを伝え共有して自由で公正な社会を実現しようとするすべての人と団体が応募可能です。対象となる取り組みは、成果物の中身と器、両面のいずれかにおいて注目すべき取り組み、またはその両方のシナジーを実現した取り組みを対象としています。第3回は、9月には選考を終えて受賞案件を公表し、受賞者発表イベントをオンラインで開催予定です。こちらの日程はウェブサイトやSNSで告知します。
それでは、本日のメイン企画「日本社会をもみほぐすジャーナリズムは可能か」に入りたいと思います。ゲストお二人をお迎えしており、著述家の師岡カリーマ・エルサムニーさんと、沖縄タイムス社編集委員の阿部岳さんからプレゼンテーションをしていただきます。
《プレゼンテーション「日本社会をもみほぐすジャーナリズムは可能か」》
◆「 海外と日本の複眼に映るジャーナリズムの現在」
師岡カリーマ・エルサムニーさん(著述家)
ジャーナリストはすべてを発信できるわけではない
師岡:みなさん、こんにちは。私は普段アナウンサーとしてニュースの発信に携わるほか、主に時事問題をテーマに新聞で毎週コラムを書いているものですから、私の仕事をときにジャーナリズムと呼んでくださる方がいるのですが、残念ながら私もジャーナリストではありません。私は事実を探しに自分で現場に出向きませんし、権力の座にある人々の発言について、その真偽を突き止めるために自分の足で歩くわけでもありません。むしろジャーナリストの方がそうやって集めて、まとめてくださった情報をもとに、いわばソーシャルコメンタリーみたいなものをする立場です。

ある意味、ずるい職業と言えるかもしれないのですが、そうは言っても、それなりに価値のある仕事だと自分に言い聞かせています。と言いますのも、新聞社やTV局、通信社などの組織に属しているジャーナリストの場合、見てきたことのすべて、自分の経験に基づく分析のすべて、自分の思ったことのすべてを発信できるわけではありません。紙面や時間の制限だけでなく、組織の立ち位置、編成の方針、ときにスポンサーなどによって発信内容は左右されてしまいますよね。制約はほかにもあります。
私たちは何を「知り損ねて」いるのか?
たとえば私はエジプト育ちですが、日本のある新聞記者の逸話があります。もう何十年も前のことですが、その新聞記者はエジプトの首都カイロに着いて最初の記事を「カイロに着くと大雨だった」という文章で始めました。エジプトは地中海沿岸地域を除くと非常に雨の少ない地域ですが、雨が降ることも年に数回あって、特に冬には大雨になることもあります。でも、エジプトというと強い日差しがピラミッドに降り注ぐ砂漠の国というイメージがあるので、「カイロは大雨」という出だしがあまりにも読者の持つイメージからかけ離れていて、おそらく記事本来のテーマからフォーカスがずれてしまうと考えられたのだと思うのですが、記事は本社に送られた時点で書き換えられて、「カイロはカンカン照り」という文章になってしまったそうです。
これは少し極端な例ですが、このエピソードの教訓は2つあります。一つ目は、ジャーナリズムはときに読者の偏見に迎合することがある、ということです。「偏見」という言葉が強すぎるなら、読者の「期待」に迎合することがある。記者の到着時に雨だったか晴れだったかは、あまり重要ではない事実ではあるかもしれないのですが、記者が伝えたかった驚きは読者に届かなかったし、エジプトにも雨が降るという情報を読者は知り損ねました。では、ほかに私たちは普段何を知り損ねているのでしょうか。
もう一つの教訓は、私の最初の論点に戻りますが、真実を追求するジャーナリストが伝えたいことがすべて伝えられるわけではないことです。伝えられた事実について記者が考えたこと、その背景などのすべてが報道機関の立ち位置や方針、制約に適合しているわけではないので、報道されないこともある。ですから、私たちのような無所属の代弁者が必要なこともあるだろうと、そう私は自分に言い聞かせて普段仕事をしているわけです。これはジャーナリストではない私が今回登壇する、まあ言い訳のようなものです。
「戦争は入念なウソの積み重ねで始まる」
さて、本題に入りますと、各国政府の機密資料などを暴くウェブサイト「ウィキリークス」の創設者で、現在はイギリスで収監されているジュリアン・アサンジさんが、かつてこういう風に言ったと言われています。「一般市民は戦争を好まない。だから、ウソをついて彼らを戦争に導くしかない。ならば、我々は真実によって平和に導かれることができるはずなのだ。これは大きな希望の源である」。この言葉を私は実際に聞いていないのですが、別のバージョンを映像で聞いたことがあります。それはこういう言葉でした。「戦争は入念なウソの積み重ねで始まる。平和は真実で達成できる」。まさしくその通りであることを、いまこの瞬間に私たちは目の当たりにしています。言うまでもなく、ウクライナにおけるロシアの、あるいはプーチンの戦争です。この戦争を国内で正当化し支持を得るために、プーチン政権がいかに強硬に言論統制を行っているかを見れば、国民が事実を知ること、そしてその事実を追求して伝える仕事が、いかに大切かがわかります。
最近、ある一つの風潮として、政府あるいは国家に対して批判的なジャーナリズムを、反社会的だとか意地悪、反日などとみなして糾弾する声が一部でありますよね。でも、平和の構築によって人々の生命や生活、それだけではなく国のインフラや産業も守られるわけですから、権力に対して目を光らせることほど愛国的な行為はないと思います。ただ、この「愛国」という言葉も私は好きではありません。多様な人々が支え合うための共同体としての日本と、国家権力としての日本を私は分けて考えます。愛国心というのは人工的な部分が多くて、人の自然な感情としての郷土愛みたいなものとは、また別の概念だと思うんです。私はエジプトの学校で教育を受け、愛国教育も受けていますから、その弊害みたいなものは身をもって知っています。
アサンジさんの発言に戻りますと、「戦争は入念なウソの積み重ねで始まる」となると、一見それほど重大ではない小さなウソをいちいち暴いていくことも大切になります。あるいは、小さなウソを論破するような、一見重要ではない小さな真実にもかならず価値がある。これはとても重要なことだと思います。海外の戦場で取材をする日本人は、日本人にとってそれほど重要な仕事をしていないかのように見られています。たとえば武装集団に拘束されて日本政府がその解放に奔走しなければならなくなると、「世間に迷惑をかけた」とか「自己責任」と言われて非難されるわけですが、私はこれはぜひとも改めていかなければいけない考え方だと思うんですね。ウソの積み重ねに対抗するには、真実の積み重ねしかないのですから、ジャーナリストの仕事は社会において必要不可欠であり、平和にとっても必要不可欠であり、その命を守るのが国家権力の役目であることは疑う余地もありません。
アルジャジーラによるウクライナ各地からの報道
普段から私はアルジャジーラを毎日見るようにしているんですけども、ウクライナ戦争が始まってからは、いつもよりも長い時間見ています。アルジャジーラは中東の国カタル――日本語ではカタールと発音しますが――の放送局ですね。創設から最初の数年は、アルカイダの取材などで優遇されていたことから、まるでテロリストご用達のような見方をされていましたが、いまでは世界の一流メディアと肩を並べる報道機関として世界的に認知されています。一時期は、経営陣の政治的あるいは宗教的理念を反映しすぎて客観性に欠けていたこともあったのですが、いまではかなり信頼できるニュースの発信者になっています。ただ、本国カタルに関する情報は、まだそんなに客観的ではありませんが。
アルジャジーラには英語放送もありますが、本丸であるアラビア語放送は、普段は数時間おきに30分のニュース、それから毎時間の正時に短いニュースを放送します。それ以外にもゲストを交えた時事問題、インタビュー、旅番組、ハイテク、スポーツ、文学、ドキュメンタリーなどの上質なラインナップが、インターネットのストリーミングでいつでも無料で見られます。ところが、いまはニュースオンリーになってしまいました。そして、ウクライナ戦争勃発後から3週間は、ほぼ9割がウクライナの報道でした。取材チームは戦闘地域も含めウクライナ各地に配備されて、戦闘地域にはアラブ人の女性記者も入っています。
アルジャジーラの報道は、加害者ロシア・自衛側のウクライナというスタンスは基本的に欧米メディアと同じなのですが、私から見ると欧米メディアより客観的です。たとえばスタジオには、ロシア人とウクライナ人のアナリストを必ず並べて迎えるということをしています。いまの国際世論、とくに西側や日本の世論では、もちろん例外もありますが、ロシアの発表については疑ってかかりますよね。事実としてロシアは加害者で強権政治、言論統制があり、プロパガンダとウソの常習犯です。しかし、私たちは被害者として必死に抵抗しているウクライナに対しては味方ですから、そのウクライナが発表することが嘘かもしれないとは、もう誰も思わなくなっていませんか? アルジャジーラの記者は、たとえばウクライナ政府が「首都近郊の町でロシアが攻撃をした」と発表したら、そこから生中継で真偽を検証するということをやっているので頼もしく思います。これは私がウクライナを疑っているからではなくて、どこの政府の発表であっても検証は必要です。しかも、これは戦争ですからプロパガンダは当たり前なのです。
視聴者の求めることが報道機関の取材姿勢を左右する
アルジャジーラ、それからBBCの記者などもそうですけれど、まだ遺体が転がっているような現場から、いま見ていることを緊張して震える声で伝えています。ときには中継の途中で攻撃が激化して、「すみません、避難します」といって中断するようなこともあります。戦争という非日常のなかに視聴者も否応なしに連れて行かれる「現場との一体感」という意味では、アルジャジーラは群を抜いていると思います。私もロシアの暴挙には日々絶望的に怒っていますし、ウクライナの人の境遇には同情という言葉では言い表せないほど深い悲しみを覚えます。しかし、そういう私から見ても今回に関しては、アルジャジーラの報道と比べると天下のBBCの報道でさえ感情的・感傷的で、少し自己陶酔的だと感じることが多々あります。
先ほど言ったように、かつてアルジャジーラは中東のCNNと呼ばれたこともありましたが、いまでは世界のアルジャジーラとして確固たる地位を獲得しています。グローバルな視聴者を対象に豊富な人材と予算を使える放送局ですから、基本的に国内向けである日本のTV局と比べる必要も、そのつもりもありません。また、私は日本の大手メディアを全部見ているわけじゃないので断言できないし、間違っているかもしれないのですが、日本のTV局は安全を考慮した報道になっていて、あまり現地に人を送っていない印象があります。TBSは最初から現地に行っていましたし、つい最近では安定した地域にNHKの取材班も入ったようですが、ニュースを見ていると各国政府の発表、それから国外に逃れた難民の取材などに比重を置いている印象で、あとは欧米の通信社から得た情報を伝えれば十分だという考え方があったのかなと思いました。でも、じゃあ欧米のメディアは絶対に信用できるのでしょうか。
あるいは、日本の大手メディアにも「これ以上の情報は、日本の一般視聴者は求めていない」という考え方が根底にあるのではないでしょうか。そうだとすると、これはメディアだけではなく受け手である私たちにも責任があると思われるんですね。「日本のテレビは国内向け」と言いましたけれど、それは言い換えると、日本の受け手は海外のニュースについて――戦争だとセンセーショナルな伝え方をされるので注目されますけれども――実はそれほど詳しい取材や分析は求めていないという、内向きな結論になってしまうのではないかと思います。究極的に視聴者や読者が何を求めるかが報道機関の取材姿勢も左右することになるわけですから、「組織が消極的なら自分が行く」と言ってフリーの日本人ジャーナリストが現地入りするなら、私たち受け手は「自己責任」ではなく、逆に「あなたのおかげで私たちの平和が少し強固になる」という認識で、それを応援するべきだと思います。
ウクライナの情報を無条件に信用していないか
私はロシアとウクライナについて、こういう風に言いました。片方が加害者であり、もう片方が明らかに犠牲者である、と。でも、そのためにロシアの発信する情報は100%ウソやプロパガンダで、ウクライナの発信する情報はすべて信用できるという風に、私たちは検証する義務を少し放棄しているのではないでしょうか。今回の戦争のほど簡単に「正しい側」に味方できる戦争というのは、なかなかありません。しかし、だからといってウクライナ側の情報、そしてウクライナを支援する西側の情報を私たちは無条件に受け入れて、勧善懲悪の悦楽に浸ってはいないでしょうか。欧米のメディアは信頼できる、と安心していないでしょうか。いつもはもう少し批判的に情報に触れているメディアリテラシーの高い人々も、今回あまりにも善悪のはっきりした戦争として始まってしまったがために、ウクライナに好意的な情報なら何でも受け入れていないでしょうか。
この戦争では、もしかしたらそれで差しさわりはないかもしれませんが、でもこれがクセになって、次の戦争までこういう姿勢をひきずってしまわないかと不安を感じます。逆に、アメリカの覇権主義を嫌うあまり西側の情報をひとくくりに拒絶して、そのためにロシア側の肩を持つ人も若干いるようですが、これはもちろん「反米なら親露じゃなきゃいけない」みたいなものではありません。
ソーシャルメディアに支えられた「アラブの春」
私はエジプト人の父と日本人の母のもと、東京で生まれてカイロで育ちました。みなさん、11年前の「アラブの春」を覚えていらっしゃると思います。エジプトでは、30年間大統領の座に居座り続けたムバラク大統領の退陣を求めて、若者を中心に大勢の市民がカイロ中心地の広場に集まりました。警察の弾圧、ときにはラクダに乗った政権派のチンピラ集団による襲撃で犠牲者も出るなかで、それでもデモを続けました。それまではずっとムバラクを守る抑圧的な警察機構を恐れていた民衆が、その恐怖の壁を打ち破って2011年にとうとう蜂起したんです。
彼らを動かしたのは、ソーシャルメディアを通じて拡散された情報でした。なぜならメディアの多くは政府にコントロールされているからです。このとき、デモ隊と政権側との間の攻防もまた情報戦でした。ソーシャルメディア対政府系メディアです。デモをする民主派は主に若者ですからインターネットを熟知している。フェイスブック、ツイッターなどのソーシャルメディアを駆使して、メディアをコントロールしている政府の情報戦争に対抗しました。インターネット時代でなければあり得ない市民の革命だともてはやされました。そして、一度は民主派が勝利しました。その地位が不動だと思われていたムバラク大統領が辞任したんです。これを「待望の民主主義の始まり」として世界が祝福しました。しかし、その後の展開は、待望の民主主義の到来とは程遠いものでした。
思想が土台となってはじめて情報は生きる
民主革命はなぜとん挫したのか。これだけでひとつのシンポジウムが必要になるような非常に複雑な問題ですが、私が思い出すのはエジプトの著名なジャーナリストであるムハンマド・ハサネイン・ヘイカル(モハメド・ヘイカル)という人の言葉です。この人はアラブ現代史の生き字引ともいうべき重鎮で、2016年に93歳で亡くなりましたが、その彼がこう言ったのですね。「インターネットは民衆を動かす。でも、思想をつくることはできない」。つまりインターネットはムーブメントをつくることはできるけれど、情報だけでは社会はつくれない。どのような社会であるべきか、それをどのように実現するか、そのような思想が土台になってはじめて情報は生きるということです。
冒頭から、受け手である私たちの偏見や固定観念や志向、つまり求めるものに報道者側の姿勢が左右されるという私の考えをお伝えしてきましたが、ここでもやっぱり行き着くのは、受け手である私たちが情報を正しく吟味し、理解し、正しく生かすために必要な教養、知識、想像力、人の立場を理解する共感力、そういったものを一人ひとりが普段から培っていかなくてはならないということです。そして、それが相乗効果として、さらにジャーナリズムを豊かにするのではないか、そういう風に思います。
***
◆「沖縄と東京から見比べたジャーナリズム」
阿部岳さん(沖縄タイムス社編集委員)
市民と連帯する新しいメディアの在り方
阿部:本日はお呼びいただいてありがとうございます。ジャーナリズム支援市民基金のみなさまには、こうして弱っているメディアを叱咤激励するイベントやアワードを設けていただいて感謝しています。いまカリーマさんが仰っていたことを一聴衆としてずっと聞いてました。本当にメディアは、市民との双方向の作用に支えられて成り立っているし、もはやメディアがこれだけ弱って権力がどんどん強くなってきているという時代のなかでは、市民との連帯というか市民に我々も頼って、期待にちゃんと応えるということが何より大事なんじゃないかなと思っています。いままでメディアはずっと偉そうにしてきて、「自分たちが決めたアジェンダに付いてこい」というか、そういう傲慢な記者も現場にはたくさんいましたよね。そういう姿勢を改めて、新しいメディアの在り方を考えていかないといけないと思っています。

加害側の自分が沖縄で記者をするということ
さて、「沖縄と東京から見比べたジャーナリズム」というお題をいただきました。私は沖縄の記者で、仕事では沖縄から一歩も出たことがないのですが、出身は東京です。25年前に沖縄タイムスの記者になりました。沖縄と東京・本土との関係でいうと、私が沖縄に来る前から、そして来た後もずっと、沖縄には基地が多すぎるんだということを沖縄は言い続けているわけですね。それを抑えているというか、反対を踏みにじって基地を建設したりしているのが日本政府で、それを支えているのが大多数の日本人であると考えると、私も加害の側にいる人間、あるいはマジョリティ側にいる人間です。そういった自分が沖縄で記者をするということがどういうことなのか、ということをずっと考えてきました。
今年5月15日は沖縄復帰50年という節目を迎えますけれども、戦後に沖縄はいったん米軍の占領下に打ち捨てられ、その間に本土は高度経済成長をして私もその恩恵を受けてきたわけですけれども、その間に沖縄は人権すら保障されない、日本国憲法も適用されないような時代がありました。そして、1972年に復帰したあとも結局、沖縄に基地が集中しているという事態が変わらない状況を、私は日本人の責任として日本人の私の仲間、同胞に伝え、この差別を止めようと訴えています。
「墜落」と呼ぶのか、「不時着」と呼ぶのか
沖縄と東京というお題ですけれども、東京と沖縄のメディアの違いで象徴的なことを思い出したので写真を共有します。これは2016年12月に沖縄県名護市の、いま辺野古の新基地建設が行われているすぐ近くの海に墜落した米軍の輸送機オスプレイの写真です。見ると機体がいろいろなところにバラバラに散らばっていることがわかります。私もこの現場にずっといましたが、写真を見てこの事故を何と呼ぶかですけれども、日本のメディアは最初、「墜落」と言っていたんですね。ところが途中で米軍が「これは不時着である」と言い始め、日本政府も「そうだ、不時着だ」と言い始めたので、日本のメディアも「不時着」と言うようになりました。
いま上から見た写真を共有しているのですが、機体はバラバラです。私はこの現場を見ていますし、東京のメディアもこれを見ているんだけれども、東京のメディアは政府発表が変わったら墜落をやめて不時着という風に言い始めたんです。いまでも、この事故について東京のメディアが言うときは、不時着水とか不時着という言い方をします。しかし、コントロールを失った機体が海面で着水してバラバラになっている、この状態を墜落と言わずして何と呼ぶのかと私は思います。私たちは現場で見たことに忠実に墜落と書きましたが、東京のメディアは政府発表に従うという象徴的なことがありました。
現場に立脚していない「発表ジャーナリズム」
もうひとつ象徴的なのは、実はアメリカのメディアも墜落と言っていたことです。米軍の準機関紙と呼ばれる星条旗新聞「スターズ・アンド・ストライプス」ですらそうでした。ですから、アメリカと沖縄では墜落と言って、その間にいる日本政府、東京のメディアだけが不時着という理不尽というか不可解な説明をそのまま受け入れていたわけです。こういったところに日本のメディアの病巣があると思います。政府の発表に従っておけばとりあえず問題はないという、発表ジャーナリズムですね。
それから「現場感がない」ということでいうと、いまたとえば台湾有事とか、南西諸島が危ないという話をするときも、同じように現場を見ずに、鹿児島県の先端から台湾までを結ぶ琉球弧をあたかも防波堤とか万里の長城のように言うことがあります。ですけど、そこに「人が住んでいるのではないか」という視点がないと思います。ですから、ミサイルを並べておけばいいと政府が言えば、基本的に受け売りの報道が続きます。この件は言い始めると長くなるのでこれで終わりますけれども、現場への想像力が欠けているというか、そもそも現場に立脚していない報道というのも問題点の一つだと思います。
政府からも、ネトウヨからも批判を受けてきた
先ほどカリーマさんが、アルジャジーラがいかに優れた報道をしているかと言われていましたが、実は沖縄・那覇を拠点にしている新聞社は沖縄タイムスと琉球新報の2つですけれども、この2つの新聞は歴代いろいろな攻撃を政府からも受けてきました。そのひとつが、いまの都知事である小池百合子さんが国会議員だった頃のものです。小池さんは、沖縄の新聞はアルジャジーラみたいだと言ったんです。なんでも反米でそれ以外にない、みたいなことを言っていました。
そのときから我々は、これは誉め言葉だなと思っていたんですけども、ただ、反米というのは事実に反しています。別にアメリカが嫌いだということではなく、軍隊は当然監視するし、すべての権力は疑ってかかるということです。それは日本政府であろうが、アメリカ政府であろうが、ロシア政府であろうが……という先ほどのカリーマさんの話と同じです。けれども、沖縄の新聞に対しては、国会議員からネトウヨまでが「偏向している」とか、あるいは「反日である」というような批判をしてきましたし、ネット上での攻撃も受けてきました。
「偏っている」と言われて委縮してはいけない
今日のテーマは、「日本の社会をもみほぐすジャーナリズム」ということですが、社会をもみほぐすジャーナリズムであるためには、まず硬直化して閉塞しているメディアの現状をもみほぐさなければいけないと思っています。たとえば「偏っている」という批判にすぐ萎縮するようなことでは、メディアの役割は果たせないと私は思うんですね。偏っているか偏っていないかというと、偏っています。それはたとえば沖縄タイムスは沖縄の報道が多くて、スポーツ報知は巨人の報道が多いといったこともそうですし、記者もそれぞれが違う人間なので偏りや主観が記事に反映されていると思います。そこで大事なのはプロフェッショナルとして、ちゃんとフェアであること。あるいは違う意見であっても、きちんと伝わるように書くこと。そういったことがジャーナリズム倫理として求められます。
ただ、「客観」とか「中立」という看板を昔に掲げてしまって、それは「もう嘘だろう」というのを読者も視聴者もみんな思っているのに、自らそれに縛られて身動きがとれなくなっているところがあります。それで、「偏向だ!」と言われたら「ううっ」とかなってですね(笑)、言い返せもしないという、メディアの不健康な現状があると思います。「偏っている」という風に批判されたら、「そう、偏っています」と言えばいい。たとえば、それは私でいえば人権や命や平和ということに偏っている、というか、それらを最優先にしていますし、そしてあらゆる権力を批判するという偏り方です。それは堂々と言っていいと思います。
マスメディアへの不信感を立て直すには
組織で言うのが厳しいなら、もうひとつの手としては、個人個人がこのように生身の姿をさらして、「こういう人間がこういうことを思いながら書いています、ニュースを読んでいます」ということも含めて、きちんと伝えるという方法もあります。組織というものが信用されない、あるいはマスメディア全体に対して不信感があるのは仕方ないことです。これまでも疑われても仕方がないようなことがありました。つい最近も朝日新聞の記者が「私は安倍晋三元総理の顧問です」と言って、外部の週刊誌にゲラ(誌面)を見せろと迫ったこともありました。こうした信頼を失うようなことをメディア自身がやってきたことを考えれば、ここから立ち直っていくためには、やはりプロセスを透明化したり、あるいは正直に自分たちの悩みやいま考えていることを明らかにして、市民に共感をしていただいたり、助けていただいたりということでしか道は拓けないんじゃないかと思っております。
***
《運営幹事、ジャーナリズムXアワードの外部選考委員を交えて対話》
「共感」は危険な言葉ではないか?
星川:実は今日、総合司会を担当する予定だった運営幹事の女性が急遽参加できなくなりまして、男ばかりでジェンダーバランスが悪くなってしまいましたが、私と運営幹事、そしてカリーマさん、阿部さんとの対話ということでお願いします。まずは運営幹事の寺中さんに自己紹介と、お二人の話を受けてのコメントで対話の口火を切ってもらえたらと思います。
寺中:寺中誠と申します。いまは大学などで教えることが多いのですが、もともとはアムネスティ・インターナショナル日本の事務局長として活動しまして、どちらかというとずっとNGO畑で活動しています。お二人の話が非常に面白かったので、それに引っ掛けて、あえて引っ掻きまわすような話をしようかなと思っています。私はもともと人権畑だったのですが、私たちが気にしていることがあって、それが完全にお二人のお話とは逆になるのです。だからこそ面白いなと思っています。

ジャーナリズム支援市民基金 運営幹事 寺中 誠
実は、人権を本来のポイントとして考えている活動、あるいはそういう動きをしている人たちは、「共感」ということに対して非常に警戒心が強いんです。「共感が大切だ」という風に言われて人権活動をされると基本的には人権活動が成り立たないくらい、共感というのは危険な言葉だと思っています。というのは、これはすぐにおわかりだろうと思いますけど、「共感できない人の人権をどうするか」を常に考えないといけない立場だからなんですね。マスメディアは割合と、その部分を本来的には拾ってくれているとは思っているのですが、ともすると「みんなの意見」とか「みんなの感覚」というものを押し付けていって、つまりマジョリティの意見にどんどん同調していって、さっき阿部さんが仰っていたような問題が発生してくるような気もするんです。
阿部さんは先ほど、ご自身が東京出身で沖縄に行ったという話をされていました。そうすると要するに、沖縄タイムスで沖縄の記事を書いていて現場はそこにあるんだけども、「ヤマトンチュ(本土の人)」であるというアイデンティティを併せ持っている。そこの部分の葛藤を感じられながら活動されている。おそらく師岡さんも、そういう葛藤をお持ちで、いろいろな活動にまい進されているんだろうと思うんですね。その場合、「人々の共感」というのをお二人はどういう風に考えていらっしゃるのかでしょうか。先ほど師岡さんは、共感が大切だということを仰ったけれど、どうでしょう? 本当にどこまで大切なんでしょうか? お二人とも、いろいろ考えるところがあるんじゃないかと思い、お聞きしたいなと思いました。
違う価値観の人を理解しようとすること
師岡:私は普段「共感力」という言葉を本当に頻繁に使っているので、そのような突っ込みをいただいたことはとても大切だと思っています。ありがとうございます。「共感」というものが人権に携わる方々にとっては危険なエレメントであるという風に見られること、それは「共感できない相手の人権も守らなければならない」という観点からだと仰っていましたが、実は私が「共感」という言葉を使うのは、まさに本質的には同じ意味なんですね。つまり自然に、何の努力をしなくても共感できる人たちというのがいる。その人たちと共感するには何の努力もいらない。でも、努力しなければ、その人の気持ちを理解することができない人もいる。自分とは考え方や価値観が全く違う人を、その人の立場に立って理解しようとすることを、私は「共感」と呼んでいるわけです。
「プーチンの人権」をどう考えるのか
寺中:ありがとうございます。実は私はドイツで育った時期があるんですが、それはまだ東西に分かれているころのドイツだったんです。私は西ドイツにいて、東ドイツというのがあったという状態でした。ですから、東西冷戦の完全な切り分けというのは目の前で見ていたし、実際に自分の現実だった。そして、日本に帰ってきたら今度は、東京ですけどそこは基地の町でした。そういう意味では、何かいろいろなことがつながってくるな、という風に思っています。
「共感」という話をしたときに、たとえばいまだったら「プーチンの人権はどう考えるんだ」ということがあります。もういま全世界いろいろなところで、プーチンの批判は毎日見ないことがないくらいボンボン出ている。もう片方で、プーチンを支持する声も出てくるんだけども、それもちょっと「うーん」というような状況で。でも、プーチンに人権がないわけじゃない。これはだから「ヒットラーにも人権があった」ということにもつながっていくわけで、その人権をどう認めていくのか、それをどういう風に押さえた発言をしていくかというのは、つねに問題になってきます。ヒットラーの人権というものを口にした瞬間に手が後ろにまわるような社会で、それをどういう風に考えればいいのかなと、私はずっと考えているところなんですね。
ですから、いまの師岡さんの、常にそういうほかの人たち、つまり自分とはまったく逆の立場の人たちの分も考えていくという話はすごく納得するところだし、でもそれをどう自分の日々の生活のなかに生かしていくのかということが難しいなとも思っているところではあります。ありがとうございました。
「寄り添う」という言葉は絶対に使わない
星川:阿部さんは、いまの話の関連で何かありますか?
阿部:はい、ありがとうございます。たぶん寺中さんはわざとこの話をされていて、「共感」という言葉を安易に使いすぎていることへの警鐘だと受け止めました。メディアでは「共感」や「寄り添う」、「絆」とかいう言葉が安易に使われています。僕は絶対に「寄り添う」という言葉は使わないんですけど、取材対象者に寄り添うことなんかできないんですよね。我々はただの横を通過する人間で、いっとき時間を共にさせてもらうけれども、本当の意味で寄り添うって「じゃあ、家族になるのか」という話じゃないですか。基地の被害者、性犯罪の被害者に対してもそうです。それを、そういう簡単な言葉でごまかしている現状がすごく問題だと思います。
ただ、「共感」という言葉は、カリーマさんも言われたように当然悪い言葉ではありません。たとえば寺中さんが言われたような「共感できない人の人権をどうするのか」という話でいうと、共感ベースだけでいえば、当然沖縄の問題は全国ニュースにはならないわけですよね。人口の99%の人が基地の被害にあっていないし、東京にも基地の町があるということですが圧倒的少数です。沖縄の問題をやると視聴者が減ると言うTV局の人もいたりするなかで、共感ベースだけではもちろんダメですが、ジャーナリストとして対象者に寄り添うのではなく、きちんとその方が言いたいことや伝えるべきことをちゃんと抜き出して、プロとして一般には共感できないような問題も共感してもらえるようにする。それが最高のジャーナリズムだと思うので、自分もそこを目指していきたいと思っています。
「共感」という概念と「フェア」であること
星川:言葉を扱う人間としては、寺中さんの突っ込みはとてもタイムリーで重要なものだと思うんだけど、もしかすると共感という言葉の意味はひとつではなくて、もっといろいろ分解していくと違う風になるのかな、という感じはします。あんまりぱっぱっと考えるのは得意じゃないので、いますぐこうだ、という風に分析はできないんだけど。
寺中:阿部さんのお話に出てきた「フェア」の話ともつながるような気がするんですね。師岡さんの仰っていた「共感」という概念と、阿部さんが仰っていた「フェアさ」――それが客観なのか中立なのかで揺れている――そのフェアというものが、これもある意味揺れる概念なんですけど、非常に似たようなところの話をしている気がしました。
師岡:つまり「相手の立場も考える」ということなんだと思います。もしかしたら星川さんが仰ったように、共感という言葉にもいろいろなニュアンス、いろいろなレベルがあって、私が考えている意味は「共感」という言葉では100%正しく伝えられないのかもしれません。たとえば私が授業などでこの言葉を使うのはどういうときかというと、ある対象になっている人がなぜそういう行ないをしたかが理解できないとき、あるいは一瞬まったく異質だと思ったときに、それでも理解しようとする。そういうことを私は共感力という風に呼んでいるのだと思うんです。そうするとフェアネス、つまりフェアであるということと、もしかしたら通じる部分はあるのかもしれないと思いました。異質なものを理解しようとする、そういう筋力だと思っています。それはやっぱり筋肉と同じで、毎日普段から鍛えるしかないと思っています。
複雑なものを単純化して白黒つけない
星川:打ち合わせのときに話が出ましたけれども、複雑な問題や事象のあり方を極端に単純化して白黒つけて「こっちが悪い」「こっちが正しい」みたいにするのではなく、複雑なまま受け止めて、さらに知ろうとする努力が必要だと思います。このウクライナの問題があって日本の市民社会の状況を見ていると、いまみたいにわからない相手を知ろうとしたり、違う意見や見方を受け止めたりする筋力みたいなものが、ますます大事だと感じるようになっています。複雑なんだから複雑のまんまというか……それだけでもダメなんだろうけど、ただそう簡単じゃないよ、っていう。
寺中:あるがままに受け止めるべきだ、というのはわかるんですが、「あるがままって何?」というのが問題だということですよね。「あるがまま」というのは、まさに報道がよく使う言葉だと思うんですけど。
星川:自分たちが「あるがまま」と思っているものを事実みたいな風に呼んでね。
寺中:その点で、先ほどの阿部さんの「いや、偏っていますよ」ということを前提にされるところと、どういう関係に立つのかを説明してもらいたいなと思います。
信頼できるかどうかは読者に判断していただく
阿部:偏っている私が伝える事実が信用できるのか、ということですよね。私は偏っていて、東京出身で……とか、そういうことも含めて、そういう私が現場に行って見た客観的事実、たとえばオスプレイが目の前で墜落していますということを伝えるときに、それが信頼できるかどうかは読者・視聴者に判断していただくしかないとは思うんですよね。ただ、私はこれまでも嘘を一個も書いたことはないですし、数字を間違えて訂正記事を書いたことはありますけども、でっち上げたことも一度もありません。25年間そういう仕事をしてきた者の言っていることを信用するかしないか、ということがひとつ、かな。「信じてください」と言ってもね、信じるかどうかはそれぞれだと思いますので。
先ほどの「単純化しすぎる」という話ですが、たとえば世界を「反日」か「親日」かで分けるような非常に浅はかな世界観にあてはめると、事実が気に入らなかったりする場合がきっとあると思うんですよね。私が目の前で起きていることを伝えても、それがその人の気に入らないこともある。たとえば、いまチャットにどなたたからのご質問も来ていましたが、今年、那覇軍港で琉球新報のカメラマンに米兵が銃を向けるという事実があって、それを報道したら「そんなわけはないだろう」とか「お前は反米か」と批判されるということがありましたが、それと一緒です。こちらは淡々と伝えていくので、あとは信じるかどうかは読者に考えていただくってことでしょうかね。
いったい誰の人権が侵害されているのか、を見る
寺中:あるがままの事実を伝えていくというのは、それ自体は観測者としての報道者がいるわけですから、その人の目によって当然ぶれることは仕方がないです。でも、ぶれても結構同じところが残っているとは思うんですよね。だから、その核の部分をぶらさないということは重要かなと思っています。
あと、別のご質問のなかで、人権を扱うときには殺戮やそういったものとは絶対に区別すべきだ、と仰ってくださっている方がいます。とてもよくわかるのですが、だから私がさっきヒットラーとかプーチンの話をしたときに、そういう部分が引っ掛かってくるのだろうと思います。でも、これはそんなに簡単じゃないんですね。まず、人権が守られる社会とか世界というのは、僕は成立しようがないと思っているんです。誰かの人権は、つねにある部分犠牲になっている。その犠牲になっているのはどこなのか、どの程度の犠牲になっているのかを、ちゃんとつぶさに見ていかなければ、大きな間違いをしでかしてしまうかもしれない。その大きな間違いをしないためにも、人権というのは制約されるものだよというところに、僕なんかは関心をもっともっと持つべきだという風に思っているんです。
ですから、「人権は大切だ」ということを言うのが人権の活動じゃないだろうと僕は思っています。人権が大切なのは当たり前なんだけど、どの程度それがいろいろなところでずらされているのかということ、それがコアなんですけど、そこを見極めることが必要かなと思っていて、ご質問いただいたところに関して強くそれは思います。人権が侵害されて構わないんだよ、という話をしているわけでは全然ありません。人権は侵害されないにもちろん越したことはないですけども、人権が侵害されたときに、いったい誰の人権が侵害されているのか。実は複数の人の、場合によっては敵対する同士の人権も侵害されているかもしれないというくらいの複雑性はあるだろうと思っています。その点では、さっき星川さんの仰った部分とも関係するんですよね。全体の複雑な構造というものを、ちゃんときちんと受け止めるということです。
ウクライナ侵攻とロシア国内のマイノリティ差別
星川:人権を冷静に比較するみたいなところ、たとえば今回もそうですけど、戦争のような事態になると、数百万の人が家を追われて避難しなくちゃならないとか、数百、数千の人が命を落とすという人権抑圧状況があります。一方で、もちろん攻めるほうにも人権はあって、たとえばロシア兵が亡くなることもつらいわけだし、プーチンにも人権がある。そういうところで、専門的な立場から言うと「人権が侵害される数」みたいなものは要素に入るんですか?
寺中:数というのは要するに規模で、インパクトという部分では影響しますけど、僕はやっぱり数の問題ではないと思っています。たとえば今回のロシアとウクライナに関して言うならば、あれはウクライナとロシアの関係を少しでも知っている人、あるいは身近に感じている人にはある意味明らかで、要はみんなどこかでつながっているんですよね。みんなどこかでつながっていて、どちらも何かに突き動かされてぶつかっている。私はどっちもどっちという意見を言っているわけじゃなくて、明らかにロシアがウクライナに攻め込んでいるのだけど、結果的にいろいろなロシア兵の人たちが言っていたのは、「入ってみたら全然聞いていたのと違っていた」ということで、その声がきちんと拾われている。その声が拾われていることも重要だし、そういう声を出していたことも重要だし、そういう関係にあったことも重要です。
ロシアのなかにも反発する人たちは当然いて動いています。ところが、その反発を押さえつける動きがある。それで結果的に、実はつい最近までロシア軍に最高司令官がいなかったことがわかった。しかも、ようやく任命された統括司令官はあちこちで人権侵害を引き起こしているいわくつきの人物であると。さらに、勇ましい声を出しているのはチェチェンでどちらかというとロシア側に付いて、ロシア政府の傀儡をしていたカディロフを送り込むとか。
これも非常にいろいろなものを象徴している気がするんですよ。戦っているのはロシア対ウクライナだったはずなのが、侵略をしているロシアのほうの勢力はだんだん違うタイプの兵隊たち、違うタイプの人々を送り始めてきています。これは実は何回もロシアが起こしているパターンなのですけど、要するにウクライナとの関係が本来的にあるロシアの人々はだんだん前から退いていって、そうじゃない人たちを出していくようなやり方です。なぜそれが可能になるのかというと、マイノリティの人々だったから。ここにはロシア国内のマイノリティに対する差別が明らかにあって、それをウクライナにぶつけるという政策が場合によっては取られているかもしれない。だから、ここをきちんと見据えていくことが、これから必要になっていく。たとえばロシアとウクライナの問題でいえば、そう思ったりします。
沖縄の米兵が一般人に銃を向けた背景
星川:ありがとうございます。もうすでに対話から質疑応答へと入ってきていますが、もう少し質問に答えていきましょうか。さきほどの那覇軍港の話については「カリーマさんはどう見ていますか?」という質問だったのですが、どうでしょうか?
師岡:これは、ちなみに距離はどれくらい離れていたのでしょうか?
阿部:200mとか250mと言われていますね。
師岡:なるほど。私がこの報道を聞いて最初に思い出したのは、何年も前ですけれども沖縄ではない別のところにある基地で、朝も夜も米軍の軍用機が飛んで騒音がひどいので住民が苦情を言ったときの話です。その苦情を市長か県知事かが基地のトップの人に伝えたところ、アメリカ側は「これは騒音ではない、自由の音だ」と答えたというんです。つまり、米軍側には「自分たちはここに日本を守りに来ているんだ」という意識があるということですよね。トップの人がそういう意識を持っていたら兵士一人ひとりも、そういう「上から目線」というか「自分はここに守りに来ているんだ」という、悪くいえば優越感、寛大にみると使命感みたいなものがあると思うんですよ。
もちろん、この兵士がプレスであれ市民であれ、一般人に銃を向けることは決して許されないことです。その決して許されないことを、なぜこの人がしたのか。顔を見ると、おそらくまだ若いですよね。兵隊になって軍事訓練ばかりしてきて、世間知らずの青年が銃を持たされて、自分が守りに来ている側の人がカメラを向けたから、「ちょっと格好いいポーズをとってやろう」くらいに思っていたのかもしれない。もちろんまったく許されることではないです。これが絶対してはいけないことだという意識を、彼らにちゃんともたせない組織としての軍隊は非常に問題です。
それと同時に、「銃を持っている自分は格好いいぞ」、「この俺たちが守るんだぞ」みたいな格好いいつもりでポーズをとって、つまりまったく深く考えていなくて、こんな大騒ぎになるとは思わなかった。そういう風にこの兵士は思っているのかもしれない、と私はその時思ったんですね。これは、「だから、その兵士を許してあげなきゃいけない」みたいな意味ではありません。ただ、個人としての兵士がそういう行為をした背景について、「自由の音だ」という発言とあわせて、そんな風にちょっと考えました。これは、ぜひ阿部さんのご意見を聞きたいところです。
「報道」と「反戦デモ」を敵対視する
星川:阿部さん、ちなみにあれは銃口がちょっとずれているからフェイクだろうという意見も出ていますが、あれは明らかにカメラマンを狙ったという絵なんですよね?
阿部:ええ、そうです。「ちょっとずれている」とかは問題外で、そもそも民間人に銃を向けている時点でおかしいわけです。いまカリーマさんからあった「自由の音だ」と米軍が言ったというのは象徴的な話で、沖縄でも同じことをずっと言っています。「これは自由の音だ」というのは彼らの常套句みたいなもので、復帰前からずっと言っていることです。自由を守りに来たという大義と実態ですよね。実態は、那覇軍港という那覇のど真ん中にある施設で、まさに報道に銃を向けている。
もうひとつ、今年2月に米軍は反戦デモの役をする米兵に銃を構えて対峙する訓練をしていました。つまり報道と反戦デモを敵視しているわけです。これは自由を守る人たちのやることではないです。自由を守るために必要なのが報道と反戦デモで、それらを敵視している訓練を組織的にやっている。カリーマさんが仰る通り、これは若い米兵一人の問題ではなく、教育をしない、むしろ敵視する教育をしている米軍という組織の問題です。
もうちょっとだけ言わせていただくと、このことを日本政府が本当は批判するべきなのですが、していません。というのは、自衛隊も「予想される新たな戦いの様相」として、反戦デモと報道を対象に挙げて内部文書に書いていたということがあります。ですから、日本政府も同じことを考えている。もっと言うと、それはプーチンがロシア国内でやっている反戦デモの抑圧や報道の弾圧と何が違うのかということでもある。アメリカもロシアも日本も、権力者がやっていることは基本的に変わらないものだと思っています。
市民が権力を監視し、そのためにジャーナリズムが機能する
師岡:いま阿部さんが仰ったように、権力にあるものがデモや報道を敵視しているというのは、すべての国で同じだと思うんですね。ただ、これは本音として持っていても、絶対に国民に知られちゃいけない、ひた隠しにしたい本音だと思います。このひた隠しにしたいはずの本音を文字にした。文字にしたら内部文書といったって、いまどき絶対にもれるんですから、文字にした時点で国民をなめていると思うんですよ。それは、なめられた国民にも責任があると思うのですが、選挙権がある有権者がこれだけ自分の国の権力になめられていたら、そりゃアメリカになめられて銃を向けられるよなと思うんですね。
決して敵対という意味ではありませんけれども、ちゃんと一般市民が国家権力を監視し、ジャーナリズムがそのために機能し、それを正しい意味で政権あるいは権力が恐れているという関係があってはじめて、米軍にしろ何にしろ、そうやってなめられないような基礎ができるんだと思う。そういう意味でも、やはり私たちの意識、それからジャーナリズムの重要性が出てくると思います。
ロシアの歴史・文化への好意までもがタブーに
星川:ありがとうございました。もう予定の時間が過ぎてしまったのですが……。
師岡:高校生の方からの質問が来ていますよね。これはとても素晴らしい質問だと思います。
星川:答えていただけますか? 質問を読んでもらえますでしょうか。
司会:最近、ロシアが悪でウクライナが善という考え方を持つ人が多いように思います。そのような風潮のなかで、ロシアの文化、言語、歴史について素晴らしいと感じても、それを発信したり、意見を言ったりすることを避けている人がほとんどです。むしろ、どのようなことでも、いまはロシアに対して好意的に感じること自体がタブーというような社会になっている気がします。戦争と歴史文化などが区別して考えられる社会にするために、ジャーナリズムはどのようなことができると考えますか?
ニュースで取り上げられたロシア人母子の活動
師岡:これはすごく難しいと思うんです。ジャーナリズムがなんとかできるというよりも、もともと私たちが持っている教養とか知識とか感覚みたいなものが重要になってくるんじゃないかなという風に思うんですね。
先日、ヨーロッパにいる私の友人が、「最近、毎日のようにロシアのクラシック音楽を聴いている。それはいま私たちがテレビで見ていることをしているロシア軍の兵士たち、ロシア人たちが野蛮人ではないということを自分に言い聞かせるためだ」という風に言ったので、私は、「でも、ホロコーストはナチス・ドイツがやったんだよ。その犠牲者だったユダヤ人は、いまイスラエルで占領地においてこういうことをしているんだよ。そして、その犠牲者であるアラブ人は、また別のアラブ人と紛争地でアラブ人同士でひどいことをしているんだよ。アメリカは原爆を落としたんだよ。そこにいたのは日本人で、その日本人もアジアでひどいことをしたんだよ。人間というのは、戦争になったときにひどいことをするもんだよ」と言いました。
これは、ロシア人だから、何人だからというものではない。戦争が導き出す人間の狂気みたいなものだという風に、私はその時に反論したんです。そういう意識をもったうえで、でもやっぱり一個人として「ロシアの文化って素晴らしいよね」と言いにくいのは、「誤解されたら困る」と萎縮してしまうというのは、いまこの瞬間だと当然だろうなと思うんですよね。だから、その人を責めることもできません。
同時に、いまジャーナリズムに何ができるかというと、どうなのでしょう? 今朝、JNNのニュースで、日本でロシア料理店を経営しているロシア人の母子が出ていました。彼女たちのところには「日本から出ていけ」とか「恥を知れ」といったメッセージがSNSで届くこともあるそうです。それに対抗する意味もあって、彼女たちがいま避難してきているウクライナ人を支援する活動をしていることを、そのニュースでは伝えていました。
こうした出来事ひとつが伝えられるのと伝えられないのでは、全然違うと思うんですよね。ジャーナリズムは、こういうことを通じて「これはロシア人全員の戦争ではない」ということを私たちにちゃんと、ことあるごとに知らせることができます。これは一つの方法ではないかと思いますが、ジャーナリズムだけの仕事ではなくて、私たち一人ひとりが自分の「心の羅針盤」を毎日のように磨いていく必要があるのだろうと思います。
社会をもみほぐすために必要なこと
司会:もう一件、ぜひ回答していただきたい質問が地方紙の記者の方から来ています。「最近、読者の窓口にくるメールや電話に、あまりよく読んでいないのか感情的で極端な内容が増えた。熟慮して言葉を尽くす忍耐を社会が失っているように感じている。記者のみなさんは考える材料を提供するのが役割だけれども、社会の読者の心をもみほぐすために必要なことは何だと思われますか」という内容です。
阿部:ありがとうございます。では短く回答させていただきます。先ほどから言っているような「反日か親日か」、「反米か親米か」という二元論、あるいは「ロシアか欧米か」みたいなことも含めて単純化する考え方が、とくにSNSを中心に多くあります。私なんかは、そんなものに絡めとられてたまるか、と思うんですけども、そういう善悪二元論の人たちにとって都合の悪い事実をどんどん出していくこと。とくに地方紙にいらっしゃるということですから、そうした事実は現場にいくらでもあると思うんです。たとえば、自由を守るはずの米軍がホスト国のメディアに銃を向けているのもその一つです。そういうステレオタイプから外れるものを探していって出していく。それが、社会をもみほぐすことにつながるんじゃないかなと思います。
師岡:エジプトで雨が降るとかね(笑)。
阿部:そうですね。「おっ」と思うじゃないですか、本当にもったいないですよね。本当にもっと面白いものが現場にはたくさんあるので、メディアのそういう型みたいなものを打破して伝えていくことが僕らの頭ももみほぐすし、いずれ社会ももみほぐすのではないでしょうか。
星川:今日はみなさん本当にどうもありがとうございました。
《閉会の挨拶》
奥田:今日は長時間どうもありがとうございました。私は運営幹事の奥田裕之と申します。対談も含め、大変面白くて示唆に富んでいると思いました。受け手である私たちの偏見や志向に報道側も左右されていくという師岡さんのお話は、これはまさに私たちがやっている活動の価値みたいなものを応援してくださっているようで、大変うれしく思いました。

ジャーナリズム支援市民基金 運営幹事 奥田 裕之
また阿部さんは、偏っているという意見に委縮してはいけなくて、偏っていてもいいが大切なのはプロフェッショナルとしてフェアであることだと仰っていました。これは逆転させて言うと、私たちのような一般市民もアマチュアリズムとしてフェアであることを守って、「偏っている」という意見に委縮せずにやるべきことをやっていくべきなんだろうという風に思います。
今日はみなさん、長時間どうもありがとうございました。